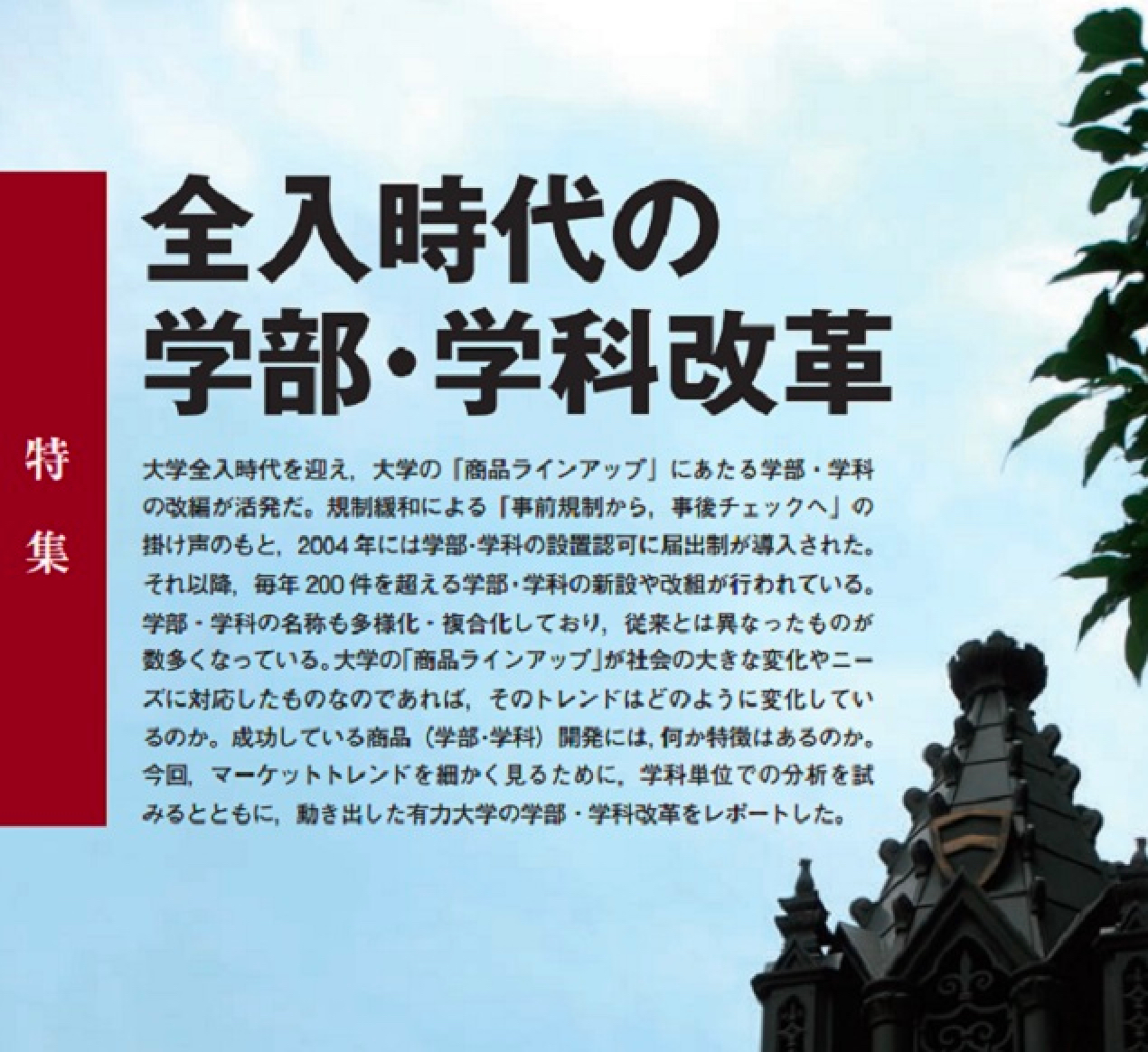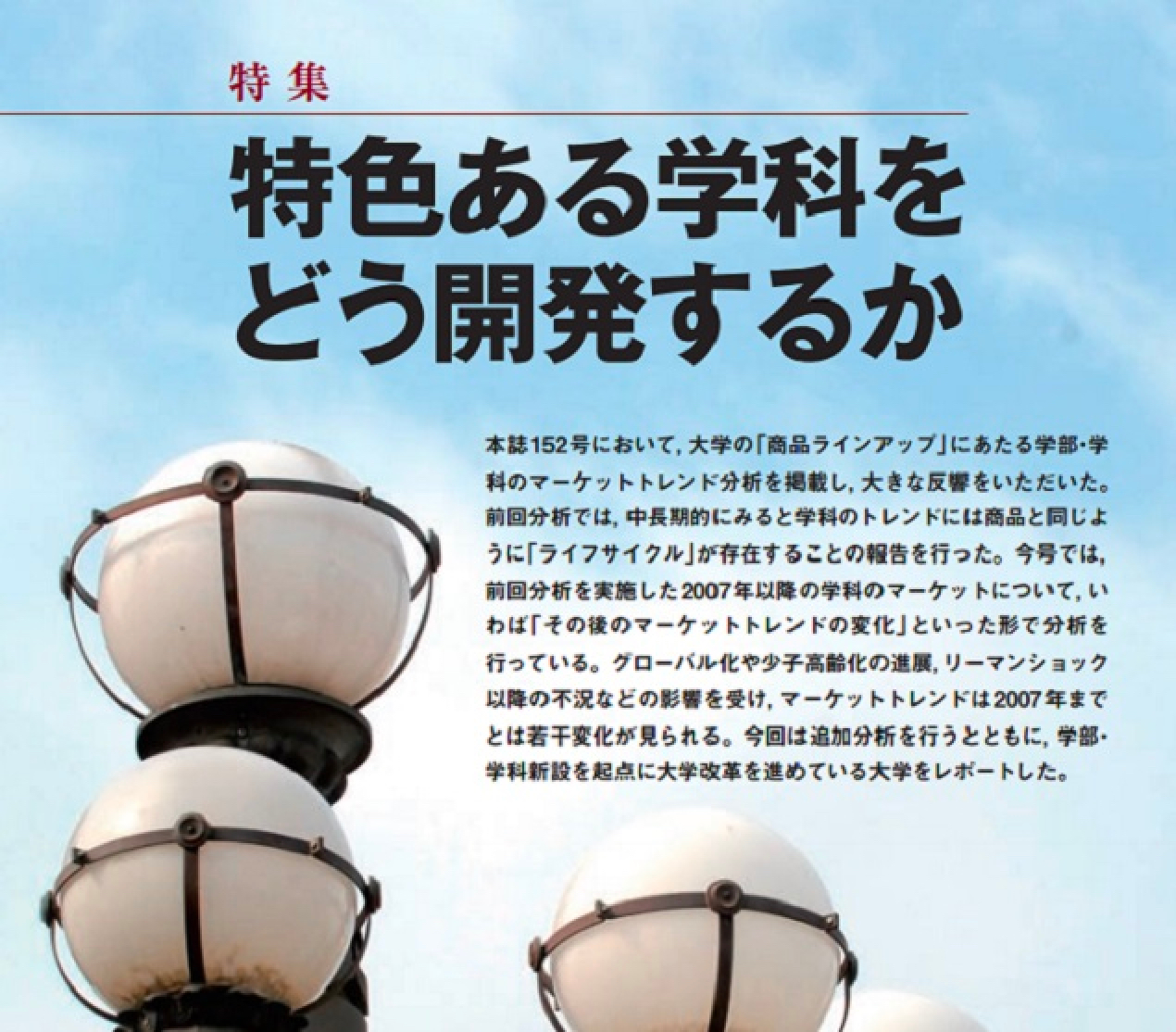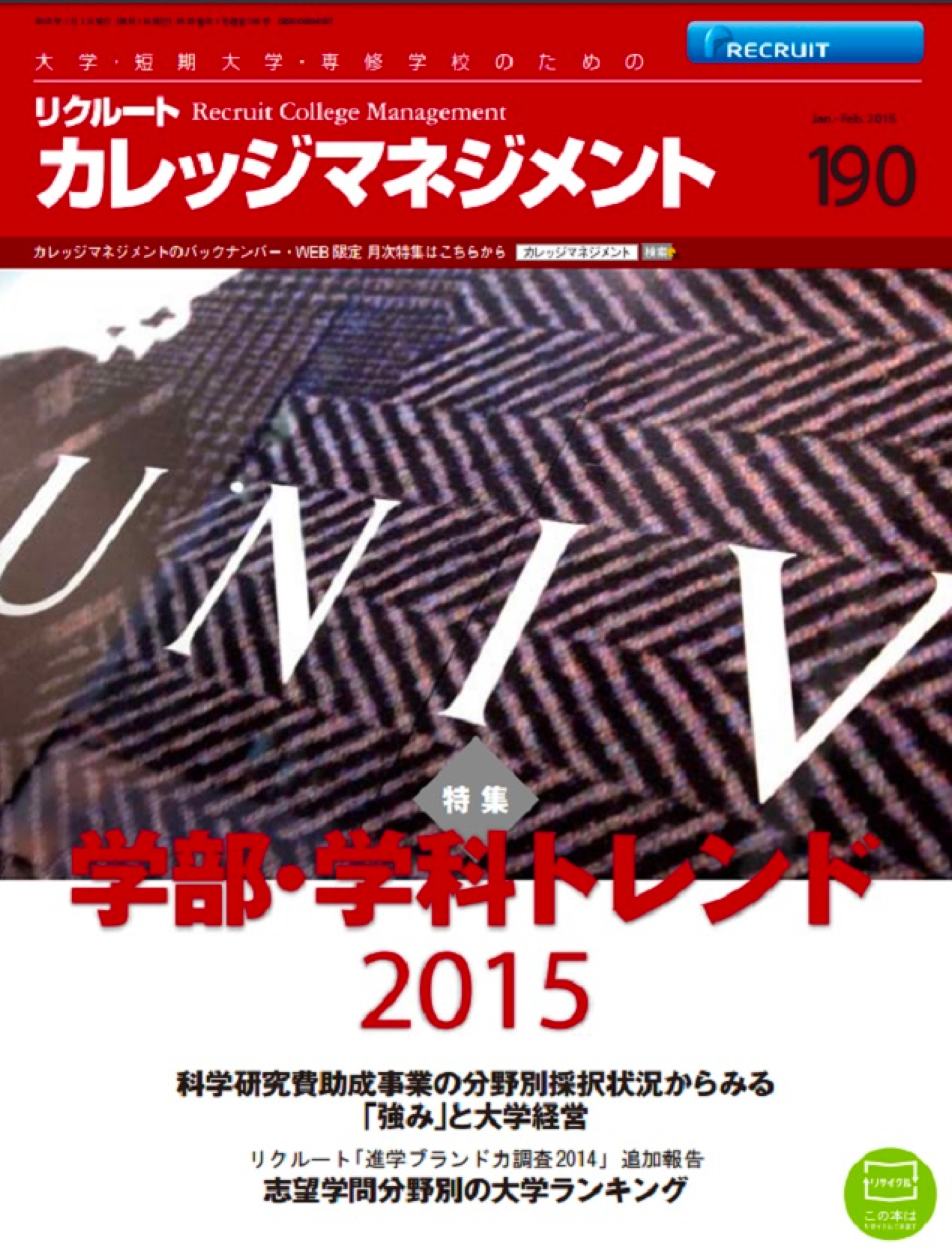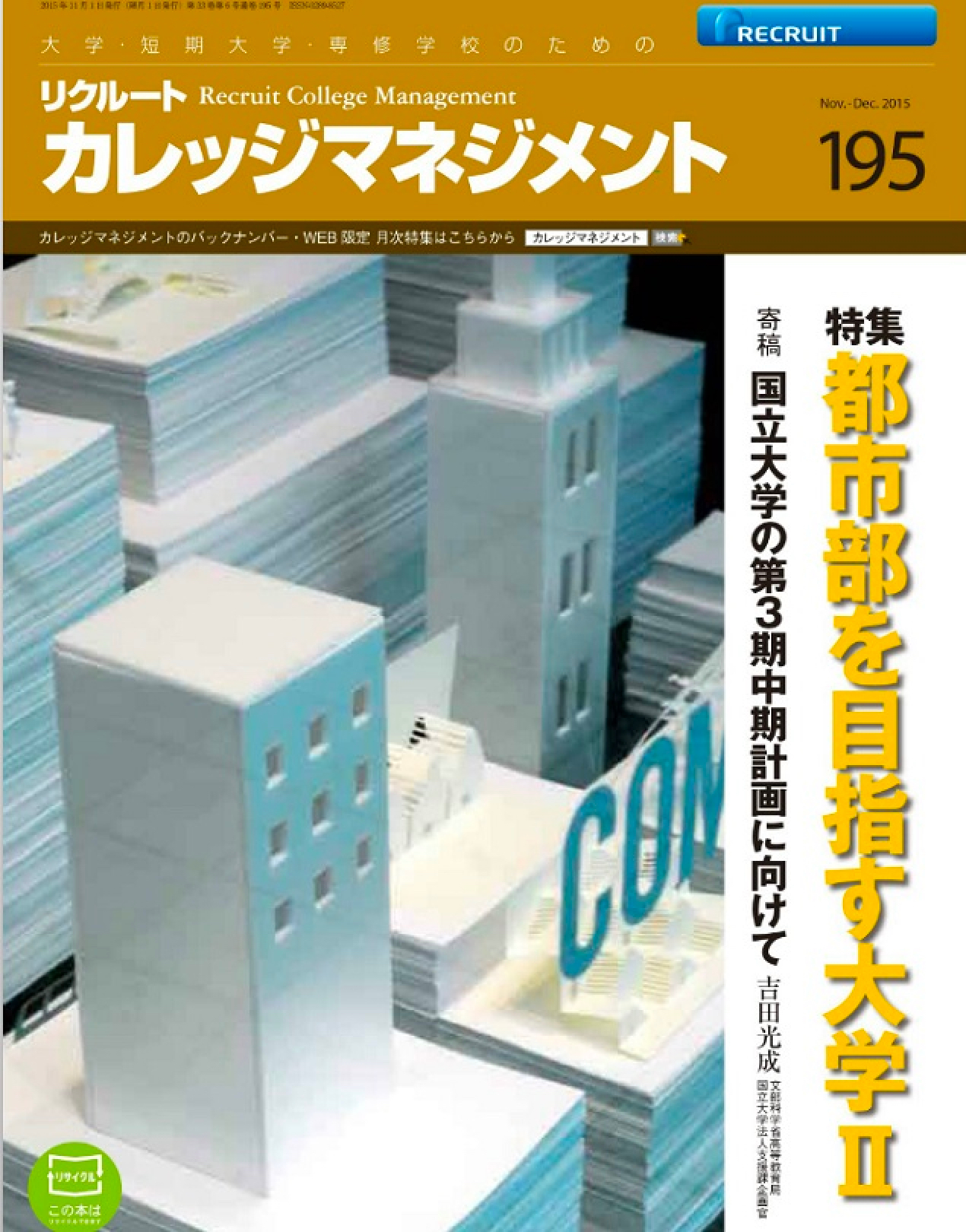RECRUITカレッジマネジメント記事
代表 寺裏 誠司がリクルート「カレッジマネジメント」に投稿した論文をご紹介します。
カレッジマネジメント【152】 2008特集 「全入時代の学部・学科改革学部・学科改編をどう進めるか」 寺裏誠司
大学全入時代を迎え,大学の「商品ラインアップ」にあたる学部・学科の改編が活発だ。
規制緩和による「事前規制から,事後チェックへ」の掛け声のもと,2004 年には学部・学科の設置認可に届出制が導入された。それ以降,毎年 200 件を超える学部・学科の新設や改組が行われている。
学部・学科の名称も多様化・複合化しており,従来とは異なったものが数多くなっている。大学の「商品ラインアップ」が社会の大きな変化やニーズに対応したものなのであれば,そのトレンドはどのように変化しているのか。成功している商品(学部・学科)開発には,何か特徴はあるのか。
今回,マーケットトレンドを細かく見るために,学科単位での分析を試みるとともに,動き出した有力大学の学部・学科改革をレポートした。
カレッジマネジメント【162】 2010特集 「特色ある学科をどう開発するか。学科のマーケットトレンドと学部・学科開発」寺裏誠司
カレッジマネジメント152号において,大学の「商品ラインアップ」にあたる学部・学科のマーケットトレンド分析を掲載し,大きな反響をいただいた。
前回分析では,中長期的にみると学科のトレンドには商品と同じように「ライフサイクル」が存在することの報告を行った。
今号では,前回分析を実施した2007年以降の学科のマーケットについて,いわば「その後のマーケットトレンドの変化」といった形で分析を行っている。グローバル化や少子高齢化の進展,リーマンショック以降の不況などの影響を受け,マーケットトレンドは 2007年までとは若干変化が見られる。
今回は追加分析を行うとともに,学部・学科新設を起点に大学改革を進めている大学をレポートした。
カレッジマネジメント【179】 2013 「全国・大都市圏・ローカル別 20年間のマーケット・トレンドと学部・学科開発」寺裏誠司
企業では、マーケティング戦略のベースとして「プロダクトライフサイクル」という考え方があり、それぞれの時期(ステージ)において適切な戦略をとることが生き残りの鍵とされている。
中長期的に学部・学科のトレンドを見ると、社会環境の変化や人材ニーズの変化に伴い、まさに商品と同じような「ライフサイクル」が存在している。
今回は、1992年~2012年の20年間にわたる推移を4年刻みで集計し直し、長期的な視点で分析を行った。この間の時代背景を見てみると、バブルの崩壊、18歳人口の減少、山一ショック、少子高齢化、ICT化、リーマンショック、急速なグローバル化、東日本大震災など、社会の人材ニーズの変化に大きな影響を与えるような出来事や環境の変化が起こっている。また、今回は人材ニーズや受験生の志向が異なることが考えられる、大都市圏とローカルエリアを比較した分析も追加した。2008年9月のリーマンショック後長引く不況、2011年3月の東日本大震災などがその後のマーケットにどのような影響を与えたのか興味深い結果となっている。
カレッジマネジメント【190】 2015 アベノミクス・東京五輪の影響で変化の兆しが見える「学科のマーケット・トレンド」寺裏誠司
企業では、マーケティング戦略の一環として、「プロダクト・ライフサイクル」という考え方がある。学部・学科も、言わば大学の“商品ラインアップ”と位置づけられる。そのため中長期的に見ると、やはり商品と同じように「ライフサイクル」が存在している。こうした学部・学科におけるライフサイクルのトレンド分析を行ってみると、社会環境の変化に大きく影響を受けていることが分かる。これまで2008年、2010年、2012年とトレンド分析を行い、大きな反響を頂いた。
今回の分析では、新たな変化の兆しが見えるものとなっている。中長期的に見ると、これまで2008年9月のリーマンショック、東日本大震災を経て、長引く不況や将来不安が、学部・学科のトレンドに大きな影響を与えてきた。しかし、2012年以降のトレンドを見ると、アベノミクスや東京オリンピック開催決定などによって、景況感が少しながらも改善(就職環境の改善)し、グローバル化の急激な進展などの社会環境の変化も相俟って、学部・学科のトレンドにも変化の“兆し”のようなものが見て取れる。
カレッジマネジメント162号(2010年5月号)の特集「学科のマーケット・トレンドと学部・学科開発」において分析した学科のマーケット・トレンド以降、1992年から2012年までの20年間のデータをもとに4年刻みでトレンド分析を行ってきた。学科のマーケット・トレンドは社会情勢の影響を受けやすく、2008年9月のリーマンショック以降の長引く不況、2011年3月の東日本大震災等の社会情勢の変化がトレンドに変化を与えてきた。本特集は、2012年の4年後である2016年に特集予定であったが、2012年12月26日の安倍政権発足後の政策であるアベノミクス、および2020年東京オリンピック開催の決定などが与えた影響か、学科のマーケット・トレンドに興味深い「兆し」のような変化が見て取れたため、2014年の中間報告を行いたい。
カレッジマネジメント【195】 2015 特集 都市部を目指す大学Ⅱ 「加速する、都市部へのキャンパス再配置」 寺裏誠司
高度成長を背景とした人口ボーナス期に、多くの大学は拡大路線をとる一方で、工場等制限法の影響もあり、広大な敷地を必要とするキャンパスは郊外を目指すこととなった。しかし、1992年をピークに18歳人口は減少に転じた。2002年に規制改革の一環として、工場等制限法が廃止されると、それを契機に大学が都心部を目指すようになった。キャンパス移転・再配置の目的は、学生募集力の強化であったり、1・2年生と3・4年生で分断されていた教育を一貫させるためのものであったりと様々である。ただ、キャンパス移転・再配置の動向を見ていると一定の傾向があることが分かる。多くの大学は、文系学部を都市型キャンパスに集約する一方、理系学部やスポーツ系、医療系といった資格取得が仕事に直結する学部については郊外型に残している。違う見方をすると、資格取得を要件とせず、学習成果が明確でない文系学部については、交通の便の良い都市型キャンパスで魅力付けをして、来るべき人口減少に向け募集力強化のテコ入れを図るという見方もできる。
2010年の「都市部を目指す大学」特集では、1970年代から90年代にかけて郊外型キャンパスを開設した大学の間で、2000年から2009年にかけて都市部に回帰する動きが活発化していることが報告されている。特に、郊外キャンパスで学んでいた1・2年生を都市部に戻し、4年間一貫教育を行って教育効果を上げようという動きが目立っている事例を紹介した。
今回の特集では、2010年以降の5年間の首都圏・中京圏・近畿圏の大学のキャンパス再配置に焦点を絞り報告を行う。1章では、各地区における都市部の収容定員の推移を見ながら、学生数がどの程度都市部に動いているかを分析する。さらに、実際に行われた移転の動きから傾向を分析する。2章では、近年の5年間にキャンパスを再配置した大学事例と志願者の動向を追いかける。3章では、今後行われる予定のキャンパス再配置計画についてまとめた。最後に4章では、キャンパス再配置の留意ポイントについて解説する。